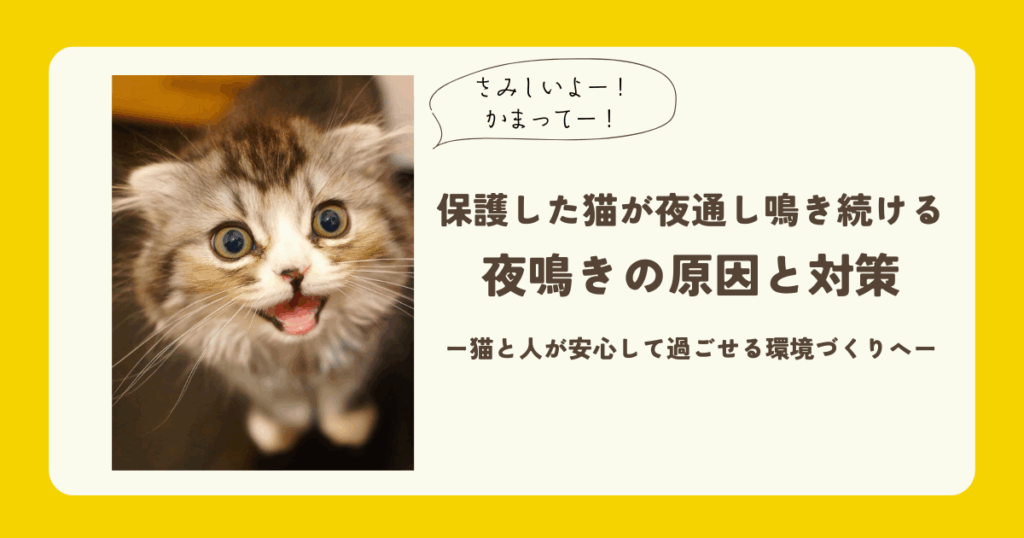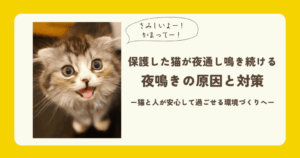今回のテーマは『保護猫の夜鳴き(泣き)』についてです。
「32歳の主婦です。つい先日、近所の公園で弱っていた野良猫を保護しました。推定で生後6ヶ月くらいの子猫です。
家には小学生の子どももいて、家族みんなで『この子を助けてあげよう』と連れて帰りました。初日はケージの中でおとなしくしていたのですが、夜になると突然大きな声で鳴き出し、そのまま朝まで鳴き続けました。
昼間は隅っこに隠れてほとんど鳴かないのに、夜になると鳴き声が止まらず、近所への音漏れも心配です。ケージから出した方がいいのか、無視した方がいいのかも分からず、鳴くたびに声をかけてしまい、逆に甘やかしてしまってるのかもと不安になっています。
実は以前、保護して半年経っても夜鳴きが続いた猫もいたので、もしかしたらこの子も…と思うと少し怖くて。子どもたちも寝不足になり、私も精神的に疲れてしまいそうです。
保護猫って、夜になると鳴く子が多いのでしょうか?もしそうなら、どうしてそうなるのか理由を知りたいし、できるだけ早く落ち着かせてあげる方法があれば教えていただきたいです。」
保護猫を迎えたばかりの飼い主さんが直面しやすい問題のひとつに、夜中に鳴き続けるという行動があります。
保護猫が鳴く理由にはさまざまな要因がありますが、この鳴き声は飼い主にとって悩みの種となるだけでなく、近隣住民への配慮が必要になる場合もあります。
特に、初めて保護猫を迎えた方にとっては、鳴き声がこれからどのくらい続くの?と不安も大きいことでしょう。
本記事では、保護猫の夜鳴きについて詳しく解説し、それに対する適切な対処法を私達の経験を踏まえて、具体的にご紹介します。ぜひ参考にしてください!
そもそもなぜ猫は鳴くのか
 猫田助
猫田助そもそもなんだけどよ、今回の質問のような猫っていっぱいるよな。なんで猫って鳴くんだい?
これは実は人間とコミュニケーションを取るためと言われています。
基本的に人がいないところでは猫は鳴かず、鳴くと人間が反応をするから鳴いているという説が有力ですね。
野良猫は、ほとんどの試験状況で極めて攻撃的かつ防御的な行動を示し、試験状況では飼い猫よりも高い鳴き声率を示した。これは、他の動物との社会化が少なく、恐怖の状況に対する感受性が高いためと考えられる。野良猫と飼い猫の音響パラメータに違いが観察された。野良猫は、闘争的な試験状況でのうなり声とシューという音の基本周波数、ピーク周波数、第 1 四分位周波数、第 3 四分位周波数において有意に高い周波数を発した。うなり声とシューという音とは対照的に、ニャーでは、基本周波数、第 1 フォルマント、ピーク周波数、第 1 四分位周波数、第 3 四分位周波数など、飼い猫のすべての音響パラメータが野良猫よりも有意に高かった。また、闘争的な試験状況では、飼い猫は野良猫よりも有意に短い鳴き声を発した。
Differences between vocalization evoked by social stimuli in feral cats and house cats – ScienceDirect(本文の内容は翻訳したものです)
これらの結果は、社会化の欠如が発声の種類の使用や発声特性に影響を及ぼす可能性があり、そのため、適切な飼い猫となるためには猫の適切な社会化が不可欠である可能性があるという結論を裏付けています。
子猫は親猫を呼ぶために鳴きますが、成猫は人間とコミュニケーションをとるために鳴きます。これは猫の社会化と呼ばれる現象で、飼い猫や、人間との心の距離が近い猫ほど鳴くと思ってください。



鳴くことが猫の社会化なんて知らなかったな〜!
夜鳴きが引き起こす問題



夜鳴きがあるとどんな悪いことが起こるんだい?別に鳴いてるだけなら問題ねぇんじゃねぇかい?
いえ、ただ鳴いているだけでも結構な影響はあります。具体的には以下の3つですね。
飼い主の睡眠不足や生活への影響
保護猫が夜通し鳴き続けると、飼い主が睡眠不足に陥ることがあります。
今回の相談者さんも、「子どもたちも寝不足になり、私も精神的に疲れてしまいそう」と言っているので、まさにこの睡眠不足は一番の問題となりますね。



猫の鳴き声ってよく耳に届くんだよね。



人間に対して呼びかけているから、伝わりやすい声に進化したんでしょうね。
近隣住民への迷惑
夜間の鳴き声は、防音が不十分な住環境では近隣住民に迷惑をかける可能性があります。
鉄筋コンクリート構造である場合は防音効果もありますが、木造の場合は確実に音漏れします。また、アパートや、マンションなどは隣との距離が近いので、尚更騒音トラブルに発展しやすいでしょうね。


猫田助でも、相談が多いのがこの猫の鳴き声による近隣トラブルです。



本能なんだものしょうがないじゃない!少しは我慢しなさいよ!
他のペットとの関係への影響
あとは保護猫が鳴き続けると、先住猫や犬など他のペットがストレスを感じる場合がありますね。犬だと音に敏感な子もいるので、猫が鳴いて、犬が吠えるという負のループに陥ることもあります。
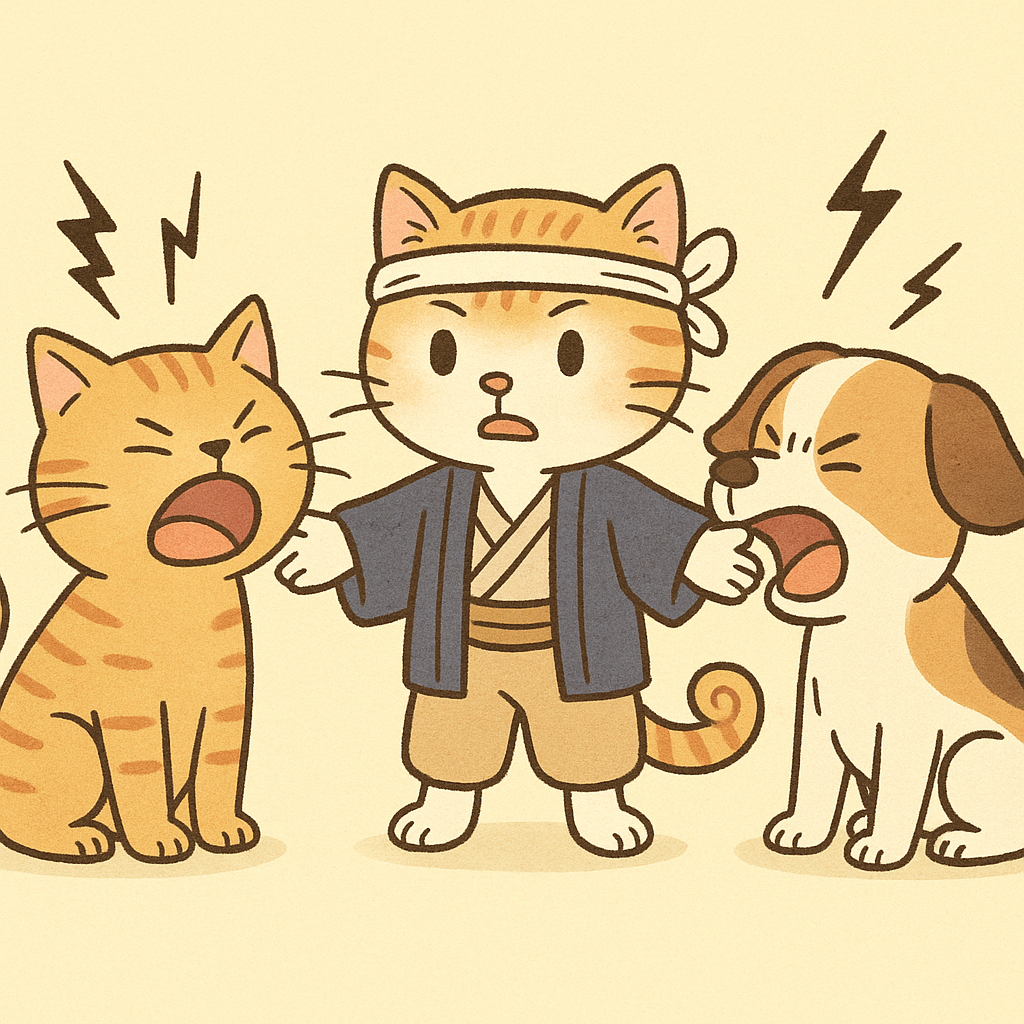
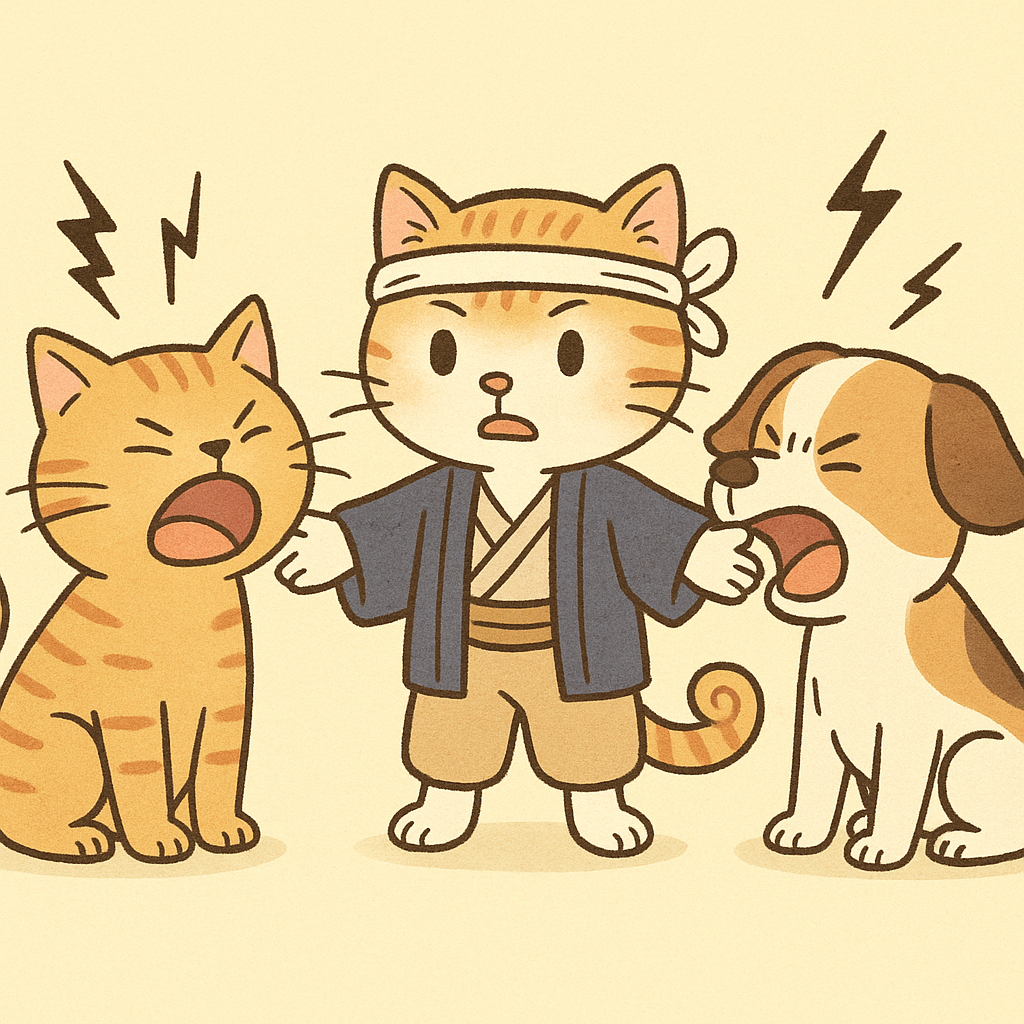
他のペットとの関係が悪化すれば、家庭内でのトラブルが増えるだけでなく、さらに保護猫のストレスが増加することも考えられます。



猫田助は猫しかいないから、ちょっとは安心できる環境なのよね。
夜鳴きへの具体的な対処法と優先度



よし、よく分かったぜ。じゃあよ、具体的な対処法を優先順位を付けて教えてほしいぜ。何から対策していくと良いんだい?
そうですね。具体的にはこのような順番で行うと良いです。
避妊・去勢手術を行う
発情期による本能的な鳴き声が、保護猫が夜通し鳴き続ける理由の大きな要因の一つですね。
相談者さんの質問文の中に『生後6ヶ月くらいの子猫』と言っていましたが、実は猫の発情期は6ヶ月くらいから起こります。保護主にとって見れば「こんな小さいのに…!?」と驚くこともあるかもしれませんが、寂しいっていうよりは発情しているのかもしれないな…っと睨んでいます。
避妊や去勢の手術を行うことで、ホルモンバランスが安定し、落ち着きを取り戻す可能性が高いかなと。


なので、まずは避妊・去勢手術を行って変化があるかどうかを見てみてください。
ケージから出してみて鳴くかどうか試す
保護猫が夜通し鳴き続ける理由の一つに、新しい環境への不安とストレスがありますね。
保護されるまで野外で生活していた猫は、自分で身を守りつつ日々を過ごしてきています。そのため、人間の家の中という新しい環境では、見知らぬ場所や音、人に対する警戒心が強くなることがあるんです。このストレスが要因で、猫は安心感を求めて『鳴く』ことで飼い主に訴えるのです。
そこで、避妊・去勢手術を行っても鳴きが落ち着かない場合は、ケージという狭い空間から外に出して様子をみてください。


ケージから出してしばらく鳴き声、鳴く頻度に変化があるかどうかをよく観察していくと改善が起こる可能性が高いなと思います。
ちなみにオススメのケージはアイリスオーヤマのキャットケージですね。扉を開けっ放しにしておくと、ストレスを抱えた時に家に戻ってくる感じで使ってくれます。
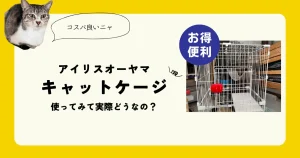
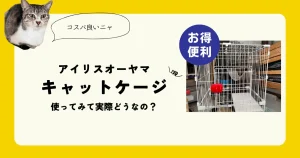
高さもあるとさらに安心感が増してくれますね。
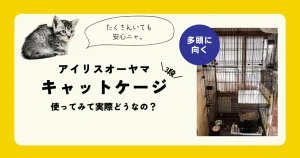
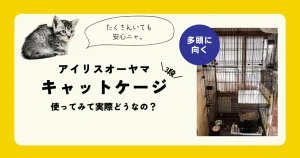
おもちゃや他の猫との触れ合いでストレス発散させる
鳴き声を和らげるためには、ストレス発散が欠かせません。猫ちゃんに安全で環境に適したおもちゃを用意し、遊びを通じて楽しみを感じさせると、環境に慣れるのが早くなります。
またたび入りのぬいぐるみキッカーは、夜中でも大きな音も出ないし、結構夢中になってくれるのでオススメですね。


一緒に遊んであげるつもりならレーザーポインターがオススメです。おっとり猫ちゃんになぜか効果が高い(笑)。
また、もし他の猫がいる場合は、徐々にお互いの距離を縮められるように一緒に過ごす方法を取り入れましょう。


最初は喧嘩したり、唸ったりすることがありますが、一週間もすると馴れてきて一緒に寝るくらいになると自然と夜鳴きをしなくなっていきます。
複数の猫と一緒に過ごさせる場合は猫の多頭飼いの注意点と準備をご覧ください。


信頼関係をつくる
最後は当たり前ですが、夜鳴きの根本的な原因が保護猫の不安である場合、飼い主との信頼関係を築くことが最も重要となります。
例えば、甘えん坊な性格なのに暗い部屋に一匹で残されると当然ながら鳴きます。もし、野良時代に人間に虐待を受けていたりすると尚更です。
このため、急ぐことなく、スキンシップや穏やかな声かけを通じて徐々に関係を深める必要がありますね。


また、無理やり抱きかかえるなどの行動は避け、猫自身がリラックスできるよう配慮してください。
こればかりは人間が安心できる存在だと分からせるしかないですね。
信頼関係の作り方は臆病な猫の飼い方。猫と仲良くなる5つのコツをご覧ください。
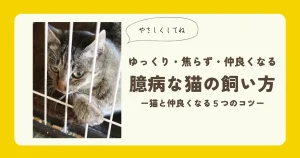
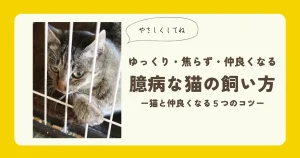



猫との信頼関係を作るのは簡単じゃないのよ。



一番は避妊・去勢手術からだな。
夜鳴きの改善にはどのくらい様子を見れば良いか



教えてもらったことを続けていきたいんだけどよ、どのくらい続ければ良いんだい?
これは猫によって違うのですが、一般的な猫(猫田助で預かる夜鳴きする猫たち)はこのくらいで馴れていきますねという例を出しますね。
2週間
保護猫を迎えてから最初の2週間は、環境の変化や新しい生活に慣れるための重要な適応期間です。
この期間中は保護された猫が、野良時代の警戒心を強く持っている可能性があります。例えば、夜通し鳴く様子が見られる場合も、何かを要求しているというより、不安やストレスが原因であることが多いですね。
この時期には、飼い主として猫に安心できる時間と空間を提供することが大切です。
寝床となるスペースを作り、ケージに柔らかい毛布やタオルを敷いたり、簡易湯たんぽを使って温かい環境を整え、体力を回復することが効果的です。
また、鳴き声には過剰に反応しないようにすることも、猫に無用な刺激を与えないためのポイントです。自分が起きている時はなるべく相手をしてあげて、夜寝ている時は鳴いていても反応しないでOKです。
一ヶ月
1ヶ月ほど経つと、多くの保護猫が新しい環境に少しずつ馴染み始めるケースが見られます。
夜鳴きが多い子の場合、鳴く頻度が完全に収まるわけではなく、新たに飼い主との関係を築こうとする段階に入ります。この時期に猫は、飼い主の行動や日々のパターンを学び、徐々に安心感を覚えていきます。
夜鳴きが続く場合でも、慣れるまでにもう少し時間が必要だと捉えることが大切です。特に保護猫が野良猫だった場合、外の環境に触れていた期間が長いほど、適応には時間がかかる傾向があります。
この期間中は、食事や遊びを通じて信頼関係を築く努力が重要となります。
このくらいの時期になったら、触れる子だったら撫でて、積極的にアプローチしてみても良いですね。触れないなら孫の手でナデナデしてあげてください。


半年
半年が経過すると、保護猫が大抵の家庭環境に慣れていくタイミングと言えます。この頃には、夜鳴きの頻度もかなり減少する可能性が高くなります。特に、避妊や去勢手術が済んでいる場合や、ストレスの軽減を意識して生活環境を整えていた場合には、保護猫が落ち着いてきたと感じられることが多いです。
ただし、猫によって性格や過去の経験は異なるので、半年経っても鳴き続ける場合は、人間の環境に馴染める猫ではないのかもしれません。その場合はTNR(避妊・去勢手術をして元の場所に戻してあげること)を検討してください。
まとめ:夜鳴きとの付き合いは長い目で!



僕もよく鳴いたりしてたなぁ。



子猫の場合は親を探してるってこともあるのかもね〜。



遊んでくれたら安心できるナァ…。



夜鳴きは他の猫と一緒に過ごすと落ち着きやすいぞ。
保護猫が夜通し鳴き続ける問題は、環境の変化やストレス、野良猫時代のトラウマ、発情期など、さまざまな理由が考えられます。特に保護されたばかりの猫にとって、環境に慣れるまで時間がかかるのは自然なことです。飼い主としては、焦らず猫のペースに寄り添い、信頼関係を築いていくことが大切です。
とはいえ、今回の相談者さんのように夜鳴きが気になって眠れない!みんな寝不足、今すぐなんとかしたい!ということであれば、逆転の発想で猫を変えるのではなく、自分たち人間からできる環境改善として耳栓を使うのも効果的です。
ただし、猫の鳴き声は平均75dBもあるため、実はかなりの騒音です。なるべく性能の良い耳栓を使いましょう。
お互いに少しずつ歩み寄って夜鳴きがおさまってくれることを祈っております。
それでは今回も、猫田助完了!