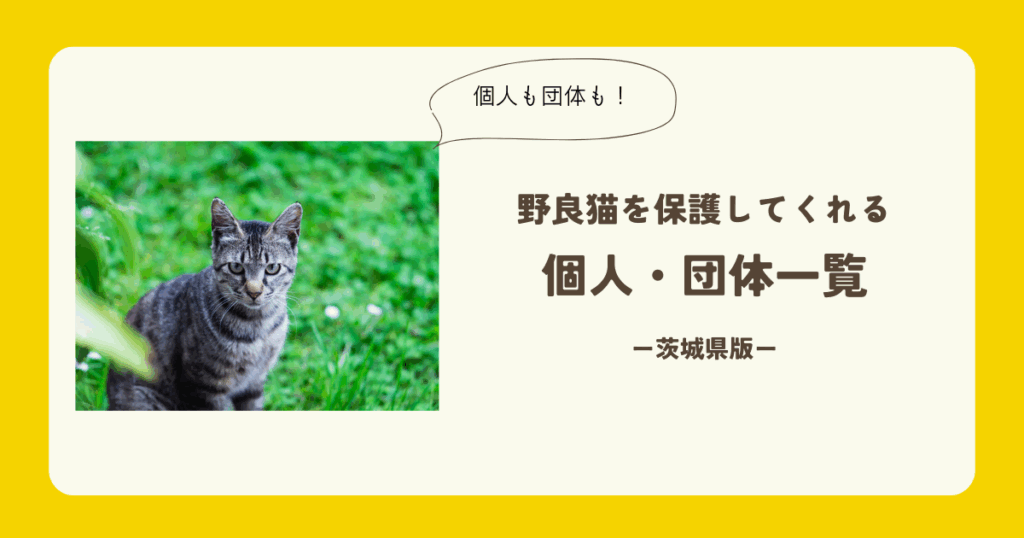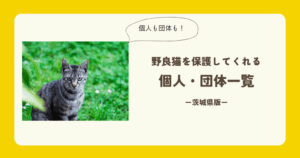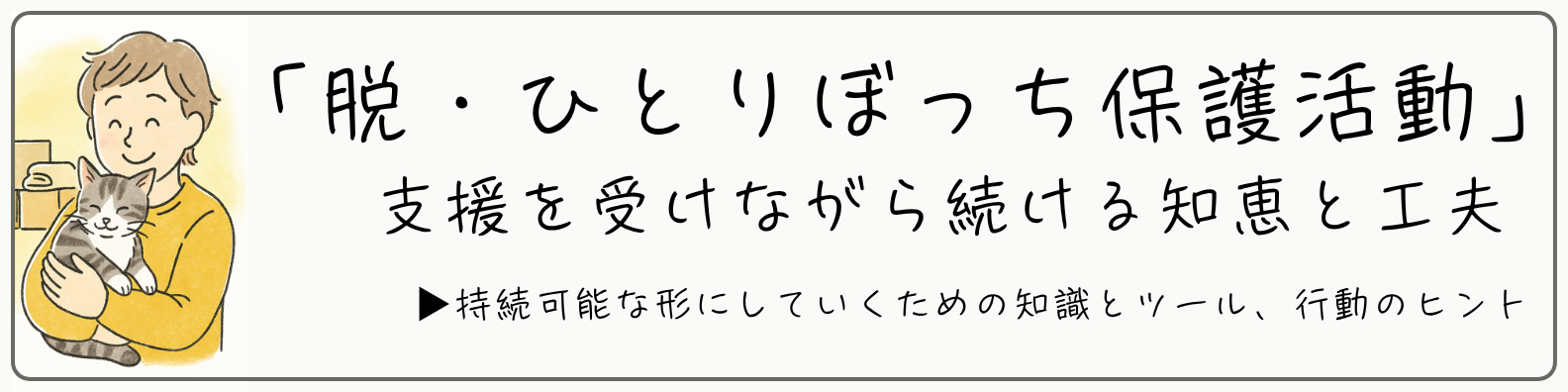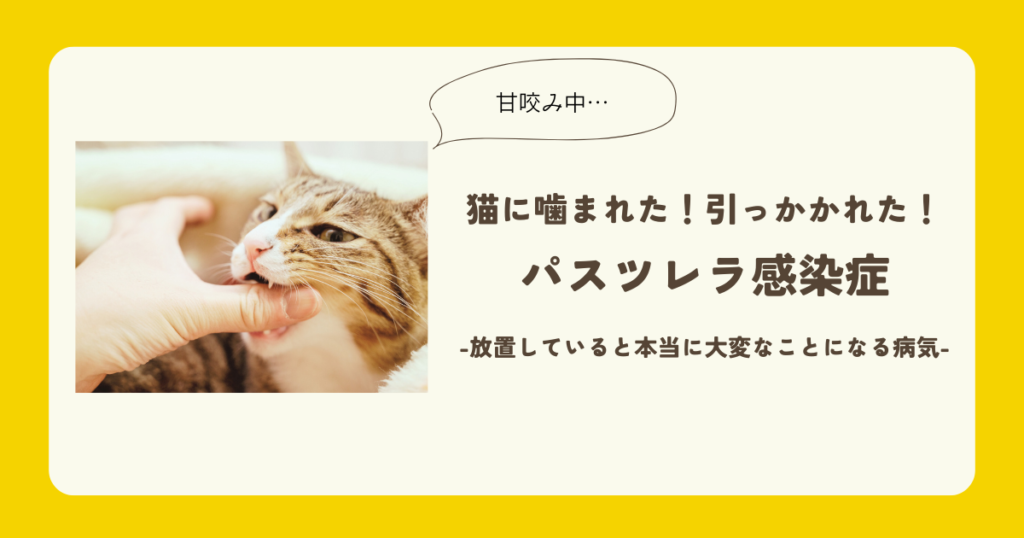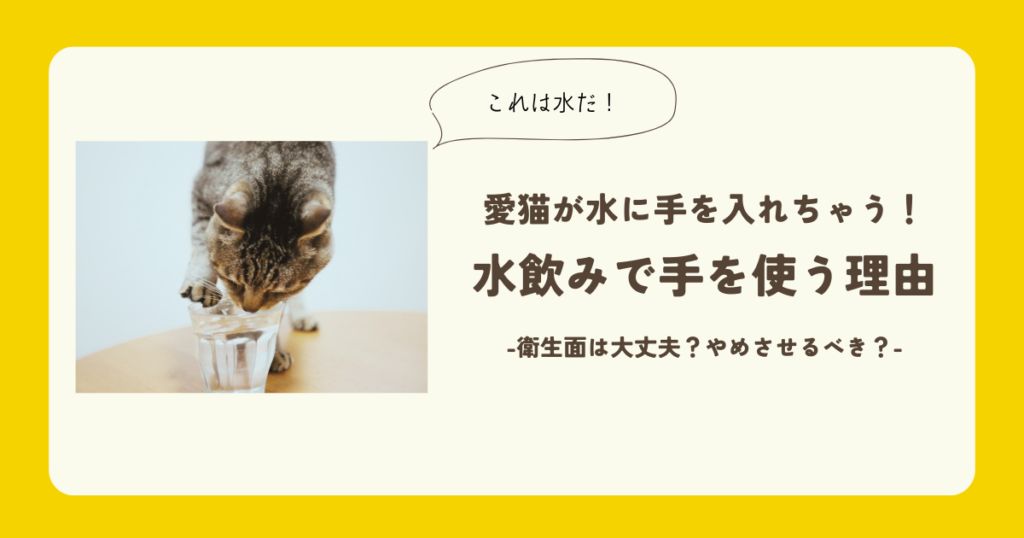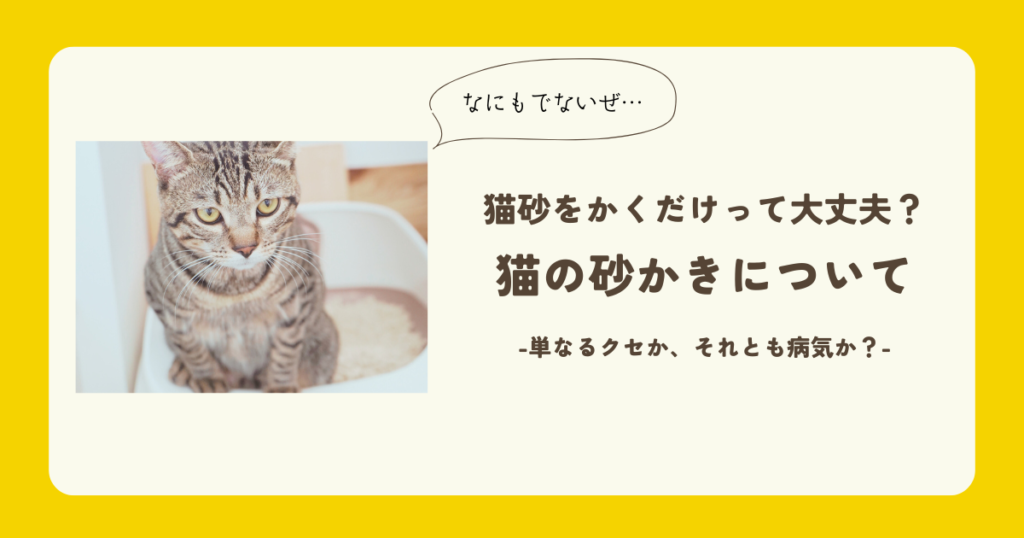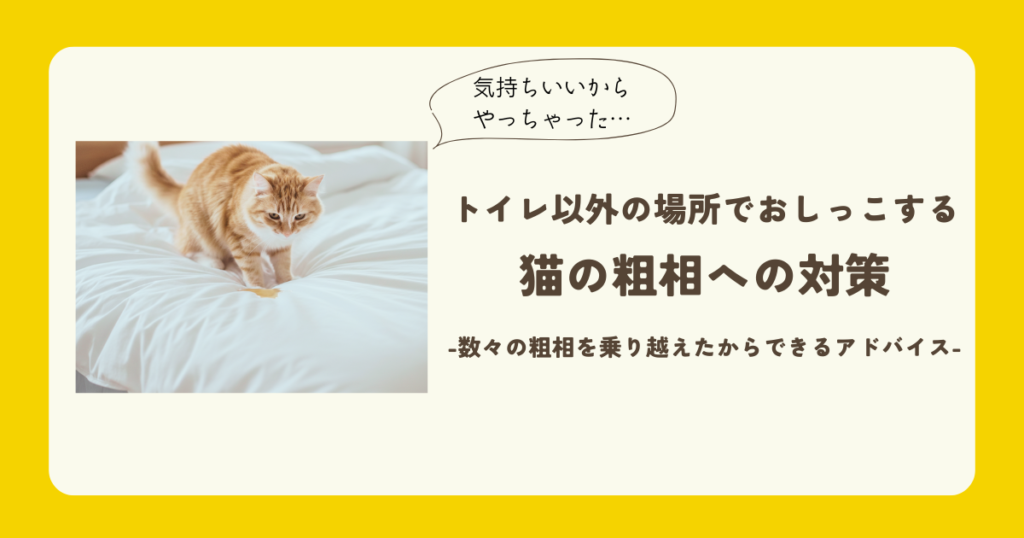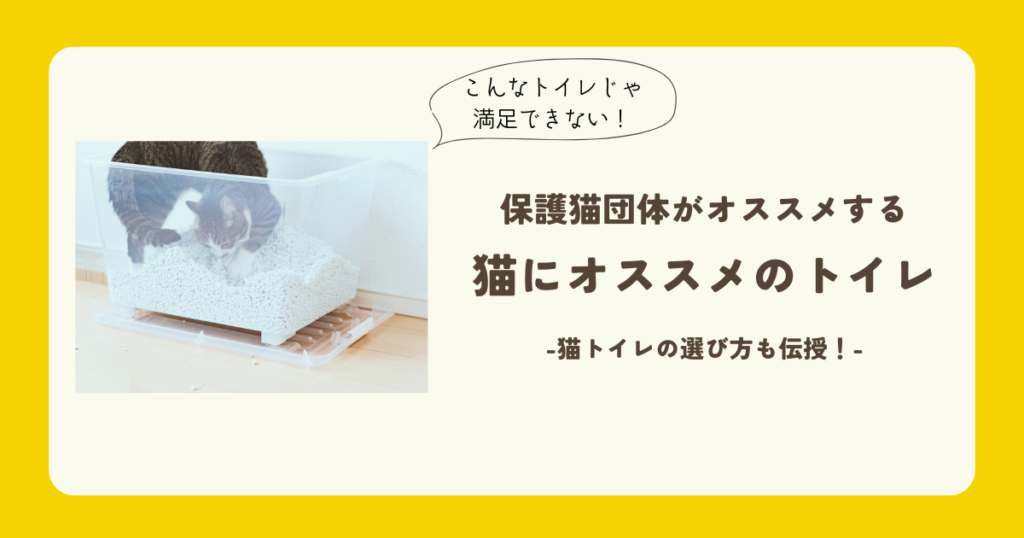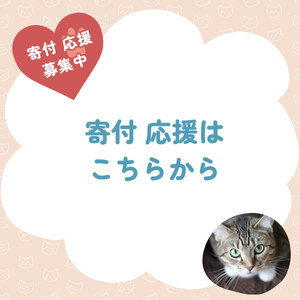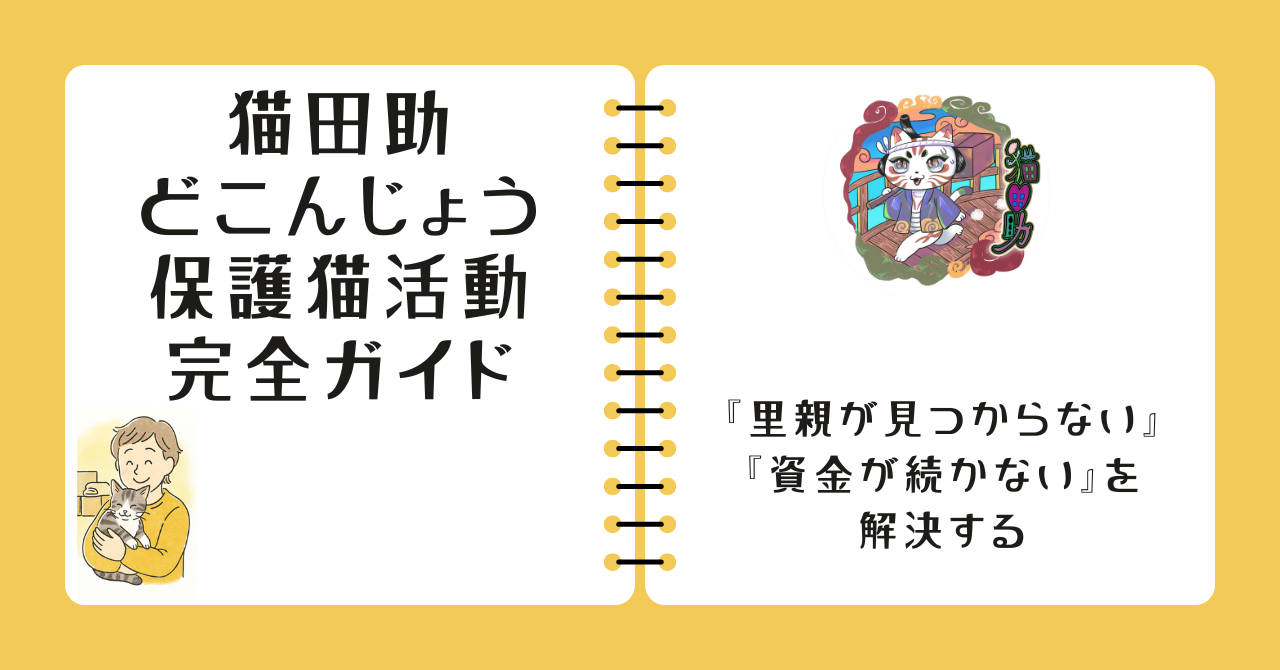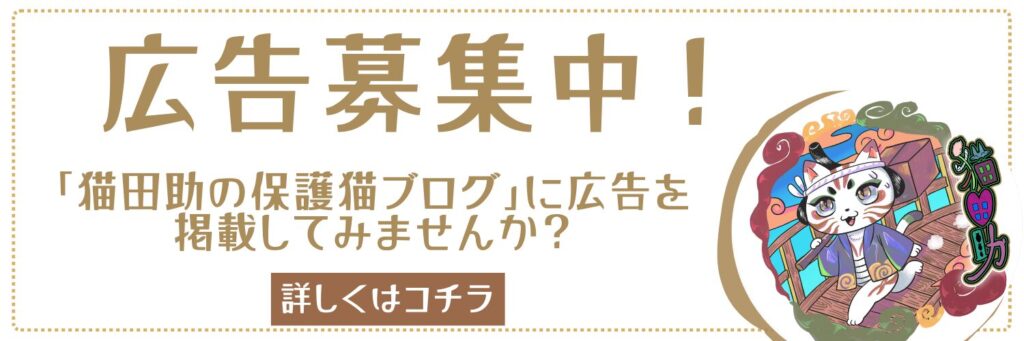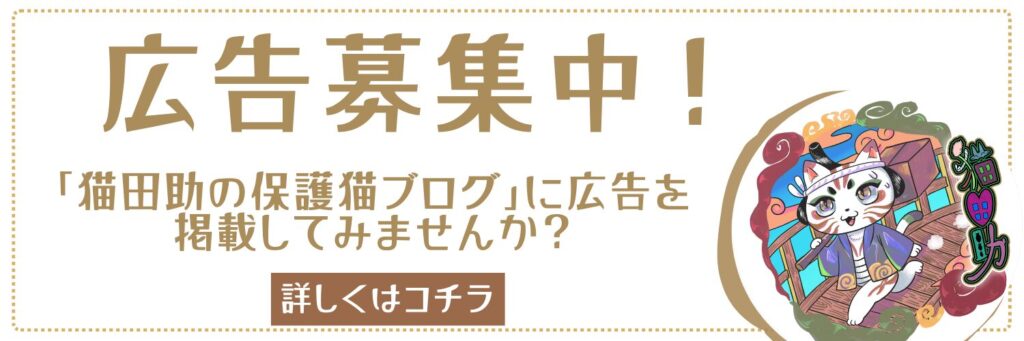今回のテーマは『茨城県で保護してくれる団体』について。
あなたは、道端で鳴いている野良猫や、雨に濡れて震えている子猫を見て、胸が締め付けられるような気持ちになったことはありませんか?その優しい心こそが、私たちが目指す『猫を助ける力』の原点です。
もしかしたら、過去に猫を飼っていたり、動物が好きでたまらない、そんな優しい方かもしれませんね。
しかし、その優しい気持ちだけではどうにもならない、現実の壁にぶつかることがあります。
猫田助さん、はじめまして。いつもブログを参考にしています!
実は、マンションの敷地に、生後間もない野良の子猫が置き去りにされているのを見つけてしまいました。まだ目も開いていないような小さな子で、このままでは衰弱してしまうと思って、なんとかしてあげたいんです。
すぐにでも保護したいのですが、私自身がペット不可の賃貸に住んでいるため、一時的な保護も長期的な飼育もできません。
そこで、茨城県内の動物愛護センターや保健所に相談したのですが、『まだ母親がいるかもしれないので、しばらく様子を見てください』と言われてしまって…。どこに連絡すれば、この子を助けてもらえるのか、途方に暮れています。
茨城県内で、緊急で野良猫を保護して、新しい飼い主を探してくれる信頼できる団体や、すぐに連絡すべき場所があれば、詳しく教えてほしいです!」
ご自身がペット不可の環境に住んでいたり、すでに多頭飼育で手一杯だったりする場合、「この子を助けるにはどうしたらいいんだろう…」と、途方に暮れてしまうかもしれません。
猫田助では、目の前の命を助けたいというあなたの行動を、全力で応援したいと考えています。
公的機関がなぜ引き取りに消極的なのかという現実的な話を知ることも大切ですが、何よりも、あなたも猫を支える・助ける一人になってほしいと思って活動をしています。
そこで今回は、そんな不安を解消するため、『茨城県で本当に頼りになる野良猫の保護先』に焦点を当てて、公的機関の限界と、すぐに動いてくれる信頼できる民間団体やボランティアを一覧にして紹介していこうかなと思います!
保健所・動物愛護センターが野良猫を引き取れない4つの現実的な理由
 猫田助
猫田助今回の相談のように保健所や愛護センターが引き取ってくれねえってのは、一体なんなんでぇ?
今回の相談のように「保健所や、動物愛護センターに持っていったら断られた」と言う人が跡を絶ちません。
しかし、知っておいてほしいのは、保健所や動物愛護センターの職員も、猫の命を救いたいという気持ちを持っているということです。
彼らがそれでも野良猫の引き取りに消極的・事務的、「様子を見て」としか言えないのには、明確な理由がある…ということなんですね。
その理由をお伝えしていきますね。
安易な持ち込みを防ぐ「終生飼養」の原則があるから
動物愛護管理法では、動物を飼う人に『終生飼養の責任』を求めています。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例
第4条 動物の所有者は,動物の本能,習性及び生理を理解し愛護するとともに,動物が人の生命,身体若しくは財産に危害を加えること又は生活環境を害することがないように,次に掲げる事項を遵守し,飼養管理しなければならない。
(1) 適正にえさ及び水を与えること。
(2) 適正に飼養できる施設を設けること。
(3) 汚物及び汚水を適正に処理し,施設の内外を常に清潔に保つこと。
(4) 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にしたり,人に迷惑をかけたりしないこと。
(5) 逸走した場合は,自らの責任で捜索し,収容すること。
2 動物の所有者は,動物を終生飼養するよう努めなければならない。
3 動物の所有者は,あらかじめ,災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るために必要な措置として規則で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例 – 茨城県
実はどの県であっても、同じような条例があり、一度飼い始めたら、その命が尽きるまで責任を持つことが飼い主の義務と伝えることが仕事なのです。
公的機関が安易に猫を引き取ってしまうと、「困ったら行政に任せればいい」という無責任な行動を助長してしまいます。そのため、行政は持ち込みに対し、非常に厳格な姿勢をとらざるを得ないという背景があります。



途中で無責任に放置される命を増やすな、っていう国のメッセージだ。厳しくても仕方ないな。
法律上、猫は「落とし物」でありトラブルを避けたいから
日本の法律上、動物は『物』として扱われ、野良猫は『落とし物(遺失物)』や『持ち主のいない占有離脱物』に準じた扱いを受け、マニュアル化されています。
遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第4条第3項では、同条第1項及び第2項の規定について、動愛法第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、これを適用しないこととされている。
所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について
これは、警察署では動物の飼養や保管に関し専門的な職員及び施設を有していないことから、専門的な職員及び施設を有する都道府県等において犬及び猫を取り扱うこととした方が動物の愛護の観点から見て適切であると考えられたためである。
もし行政が安易に引き取ってしまった後、「実は飼い猫だった」「返してほしい」といった所有権をめぐるトラブルが起きた場合、その責任を負うのは引き取った側になってしまいます。
公的機関はこうした法的なトラブルを避けるために、個人からの持ち込みには慎重にならざるを得ないのです。



猫ちゃんに所有権なんて、悲しい話だけど、行政としては無視できないルールなんだね…。



トラブルになったら警察沙汰になるから、それを避けているのね〜。
収容施設のキャパシティ(頭数・感染症リスク)の限界があるから
命を助けるための施設の収容力は無限ではありません。
茨城県内の動物愛護センターや保健所が持つ収容スペースや人員は限られています。もし野良猫を無制限に引き取ってしまうと、本来保護すべき『緊急性の高い猫=ケガ・病気で動けない猫や、子猫』を収容できなくなってしまいます。
また、野良猫は様々な感染症(猫カリシウイルスや、猫ヘルペスウイルス、猫エイズ、猫白血病、ノミ・ダニなど)を持っている可能性が高く、すでに収容されている健康な猫たちに病気を広げてしまうという、集団感染のリスクが非常に高いのです。



感染症のリスクを考えると、他の猫たちを守るためにも、簡単に引き取れないんだねー。
「命の選別」につながる可能性があるから
最も目を背けてはいけない現実として、公的機関に引き取られた猫のすべてが、新しい飼い主のもとへ行けるわけではないということです。
収容数には限界があり、長期間譲渡先が見つからない猫は、残念ながら安楽死処分となってしまう可能性があります。
行政が引き取りを渋るのは、「命を救えない可能性がある場所に、安易に持ち込ませたくない」という、最後の防波堤としての役割を担っているからでもあるのです。
預けた側としては引き取り=必ず助かると思いがちですが、そうではない現実があることをしっかり自覚しないといけないでしょう。



預けてそれで終わり…というわけにはいかないんだよね。



引き取りを断るのも、命を無駄にしないための苦渋の決断なのかもしれないわ。
保護猫団体に相談・お願いする時の3つのマナー



行政はいろいろとあるってことは分かったけどよ、次は頼れる保護猫団体なんだが、お願いする時に気をつけておいたことはあるんかい?
保健所が引き取れない今、野良猫を助ける頼みの綱は、地域で活動している保護猫団体や個人のボランティアです。
しかし、行政から金銭的な援助をほとんど受けず、自己負担と善意で活動しているという現実を知っておいてください。(もちろん、猫田助もそうです)
一方的に任せて終わりではなく、その負担を少しでも減らし、猫を助けるための『チームの一員』として協力するために、以下のマナーを守って相談しましょう。
まず、『本当に保護するべきか』を冷静に検討する
野良猫が健康で自活できており、TNR活動が行き届いている地域にいる場合、安易に保護することは、その猫の自由を奪い、団体側の負担を増やすことにもなりかねません。
以下の点を確認し、本当に緊急性があるかを冷静に判断しましょう。
- 母猫がいる可能性
特に子猫の場合、近くに母猫が隠れていることが多いです。すぐに連れ去るのではなく、数時間遠くから観察しましょう。 - TNR済み(さくら猫)か
耳のVカット(さくら耳)があれば、すでに不妊去勢手術が済んでおり、その地域で一代限り生きることを許された猫です。そのまま見守ってあげることが最善です。
他にも保護するべきかどうかのチェックする事柄はたくさんあります。詳しくは野良猫保護の判断基準をご覧ください。
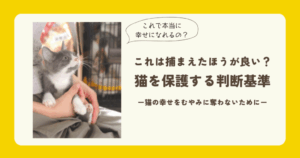
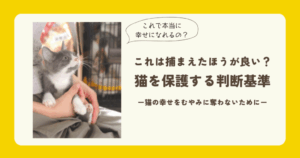



安易な保護が、かえって猫の負担になることもあるのよ。



まずは立ち止まって考える優しさも必要よ!覚えておきなさい!
状況を正確に伝え、具体的な情報を提供する
保護猫団体が最も必要としているのは、『時間』と『情報』です。相談する際は、感情論ではなく、以下の具体的な情報を冷静に、簡潔にまとめて伝えましょう。
| 項目 | 伝えるべき内容 |
|---|---|
| 猫の状態 | 子猫か成猫か 怪我や病気の有無、目やになどの具体的な症状。 衰弱しているか |
| 場所と状況 | どこで見つけたか 母猫や兄弟がいるか いつからそこにいるか |
| あなたができること | 一時的に自宅で保護できるか(期間) 病院へ連れて行くことは可能か(費用負担の有無)。 |



「可愛そう」だけじゃ動けないの。私たちが動くための情報と準備が一番大事よ〜。
医療費や運営費の負担について協力の姿勢を示す
保護猫団体の活動資金は、寄付やボランティアの自己負担に頼っています。そのため、「ただ引き取ってほしい」という一方的な依頼は大きな負担となり、断られる原因になりかねません。
- 初期医療費の負担
団体が引き取る前に、最低限の検査やワクチン、ノミダニ駆除などの初期医療費を『保護したあなたが負担する』意向を伝えましょう。これが保護する際に最も役立つ協力になります。 - フードや物資の提供
支援として、猫用のミルクやフード、トイレ砂、タオルなどを提供する提案も有効です。 - 寄付
物資はお金に変えにくいので、純粋に寄付をしていただけるのが最も助かります。



命を助けるには金がかかる。困った時にはお互い様だから、相手の立場になってお願いするのが大切だぞ。
一時的な保護(預かり)を検討する
基本的に保護猫団体側のキャパシティが満杯であるケースがほとんどです。これは同じように『保護してほしい人』がたくさんいるからで、特に繁殖シーズン(4〜6月、9〜10月)は難しいでしょう。
そのため、保護を依頼して、すぐに引き取りを依頼するのは難しいと思ってください。
もし、あなたが自宅で安全な場所(ケージなど)を確保できるなら、引き取り手が見つかるまで一時的に預かるという提案をしましょう。
『単純な引き取り』ではなく『見つかるまでは預かる』と申し出るだけで、団体からの協力が得られやすくなります。
茨城県の保護猫活動団体一覧



そいじゃあ、茨城県で保護してくれるかもしれねぇ団体を教えてくれねぇか?
茨城県で野良猫の保護・譲渡・TNR活動を精力的に行っている個人・団体を以下にまとめます。活動の状況や対応可能エリアは日々変わるため、連絡する際は必ず公式サイトを確認してください。
保護猫団体は、職員やスタッフがいる行政機関とは違い、善意のボランティアによって支えられています。連絡する際は、相談・お願いする時のマナーを強く意識してください。
茨城県央
水戸市、大洗町、ひたちなか市、小美玉市、笠間市で活動している個人・団体があります。
| 団体名 | 主な活動エリア | 特徴と活動内容 |
|---|---|---|
| 保護猫Cafe eden | 水戸市 | 水戸市で「猫と人の新しい出逢いの場」を提供する保護猫カフェ。猫たちがストレスなく普段通り過ごせる環境を大切にしています。カフェの収益は保護猫の飼育費や医療費、新たな保護活動に活用。訪れる人が猫とふれあいながら新しい家族を見つける譲渡活動に力を入れています。 |
| ねこサポ茨城 | 水戸市(茨城全域) | 地域猫活動の助っ人として、野良猫の捕獲に特化したサポートを提供。「一人で捕獲するのが不安」「何度も失敗している」といった方の相談に応じ、現地での状況確認から捕獲の準備・計画までを支援します。里親探しは行っておらず、消耗品とガソリン代の実費で依頼が可能です。 |
| 茨城の保護猫里親探し 猫田助 | 水戸市(主に関東全域) | 水戸市を本拠地とし、保護された猫と里親を繋ぐ手伝いをしています。欲しい方が居た場合、県内外に関わらず里親に直接お届けするのが特徴です。(野良猫の保護・捕獲は行っていません)。 |
茨城県南
つくば市、石岡市、龍ケ崎市、阿見町・美浦村、取手市、利根町で活動している個人・団体があります。
茨城県北
日立市、常陸太田市、高萩市で活動している個人・団体があります。
茨城県西
古河市、結城市、常総市、坂東市、五霞町で活動している方がいます。
茨城鹿行
鉾田市、鹿嶋市、潮来市、神栖市で活動している方がいます。
まとめ:茨城県各地で保護猫活動をしている方へ感謝して連絡をしよう



依頼先についてだったけど、どうだったかなー?



動物愛護センターにも事情があるのよね。



保護したいのに、保護できる環境がない…って悩む人多いんだなって思ったよ。



自分一人よがりじゃ駄目なのよ!
相談をくださった方のように、ペット不可という賃貸に住んでいるのに、マンションの敷地でつい見つけてしまった…という方は非常に多く、どうしようと途方にくれてしまう方もいらっしゃいます。
そういう時に保護猫活動をしている方は非常に頼りになりますので、ぜひ頼ってみてください。
どちらかというと、「保護して!」より、「相談したい」と自分で解決する意思がある人のほうがありがたいので、そういう心持ちで連絡してみると良いでしょう。
それでは、猫田助完了!