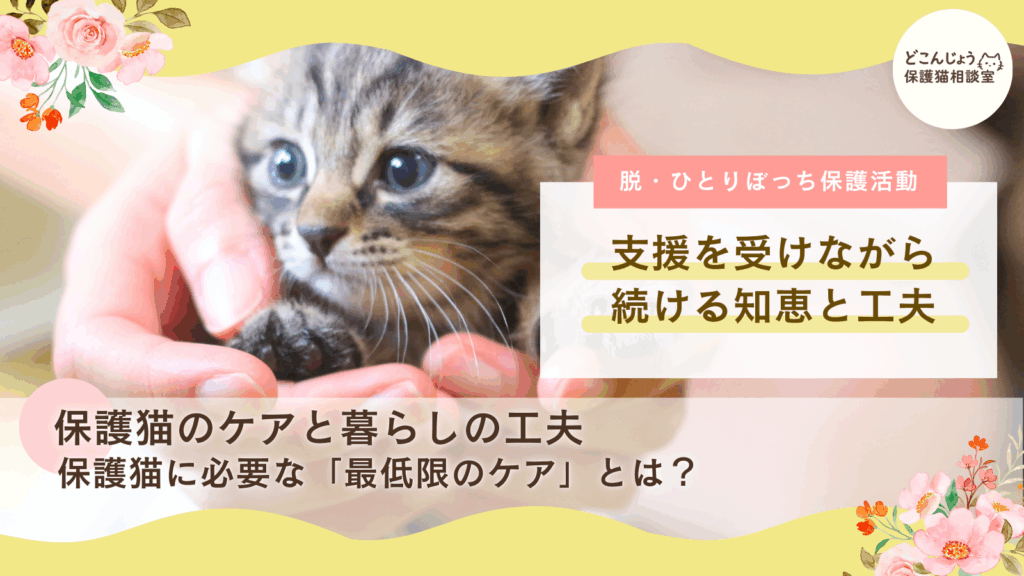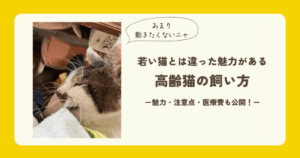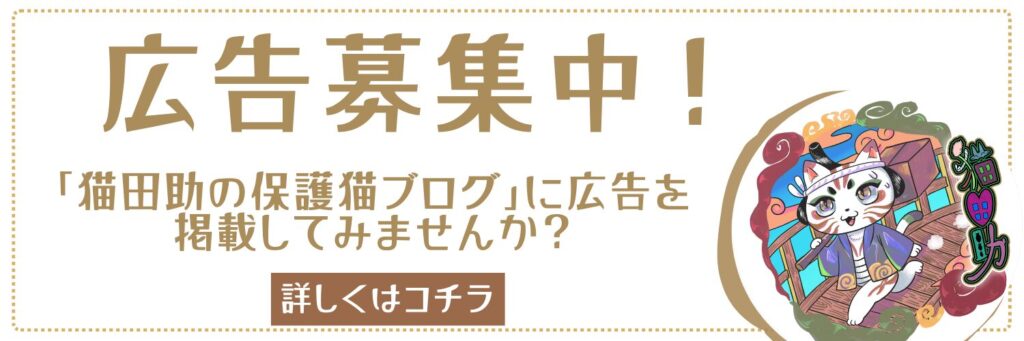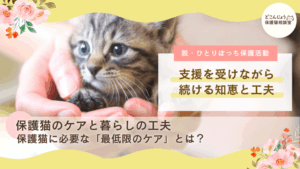保護された猫にとって、まず最初に必要なのは 安全な空間と健康状態の確認です。
体調を崩している子や、外で過酷な環境を生き抜いてきた子も多く、早期に医療ケアを行うことが命を守る第一歩となります。
最低限でも必要な医療ケア
まず初めに、猫を保護してお家に迎えた場合に必要なケアは4つ。
- ノミ・ダニ駆除/駆虫薬投与
→ 多くの野良猫には寄生虫がついています。まずは駆除を。 - ウイルス検査(エイズ/白血病)
→ 他の猫と接触させる前に実施。感染状況を把握するためにも大切です。 - ワクチン接種(3種または5種)
→ 室内にいてもウイルス感染リスクはあります。早めの接種が安心です。 - 必要に応じた治療(風邪・外傷など)
→ 保護時に鼻水や目やにが出ている場合は、すぐに受診を。
野良猫は野生動物と同じ暮らしをしていると言ってもいいです。
命をつなぐために、必死に生き抜いてきました。
どんな状況で何を食べ、どんな動物と接触していたのかわかりません。
だからこそ、お家に迎え入れる準備はしっかり行いましょう。
①ノミ・ダニ駆除/駆虫薬投与
ノミ・ダニ駆除や駆虫薬の投与をしない場合、猫自身の健康だけでなく、人や他の動物にも影響を及ぼすリスクがあります。
- 1. 猫の健康リスク
-
- 貧血や衰弱
ノミが大量に寄生すると、吸血により貧血を起こし、特に子猫は命に関わることもあります。 - 激しいかゆみ・脱毛・皮膚炎
皮膚が赤くただれたり、毛が抜けたりします。 - 瓜実条虫(サナダムシ)への感染
大量に寄生した場合、下痢や血便がでることがあります。 - 下痢・嘔吐・栄養不良
寄生虫(回虫・鉤虫など)は、栄養吸収を妨げて発育不良や体調不良の原因になります。
- 貧血や衰弱
- 2.人間への健康リスク
-
ノミ刺咬症
人間も刺されると強いかゆみや発疹が出ます。特に乳幼児や高齢者は注意。皮膚炎・感染症の媒介
咬み傷や引っ掻き傷からの病原体の侵入や、ダニ・蚊などが感染動物から人間への吸血などで感染します。動物由来感染症による人への感染
特にトキソプラズマ症は妊娠中に初めて感染すると胎児に感染する可能性があります。また、回虫も人間が感染すると幼虫が移動する臓器によって様々な症状を引き起こします。
②ウイルス検査(エイズ/白血病)
先住猫がいる中で保護猫を迎える場合、最重要ステップの一つです。
- 1. 他の猫に感染させないため
-
- FIV(猫エイズ)やFeLV(猫白血病)は、主に猫同士の接触(ケンカ・グルーミング・食器の共有など)でうつります。
- 陽性の子を知らずに他の猫と同居させると、感染が広がる危険性があります。
特に白血病(FeLV)は感染力が強く、進行が早いため、早期の確認が必要です。
- 2.猫自身の健康管理のため
-
- 特に猫エイズは、陽性であってもすぐに発症するわけではありませんが、免疫力が下がると感染症や腫瘍などにかかりやすくなります。
- 検査で陽性がわかれば、ストレスや体調管理により一層配慮したケアが必要になります
完全に家の中に入ってから2ヶ月、または生後4ヶ月未満の子猫は偽陽性・偽陰性が出ることがあるため、後日再検査が必要になることもあります。
③ワクチン接種(3種または5種)
保護猫は、過酷な外の環境や栄養状態の乱れによって、免疫が低下していることが多いです。
少しのストレスでも体調を崩しやすいため、ワクチンで“防げる病気”から守ることはとても大切です。
殆どの場合は3種ワクチンで十分です。
猫汎白血球減少症(パルボウイルス)、猫ウイルス性鼻気管炎(猫ヘルペスウイルス)、猫カリシウイルス感染症の予防ができます。
①致死率が高い:パルボウイルス感染症
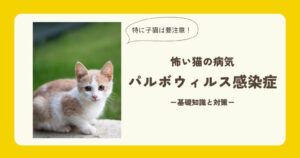
②完治が難しい:猫ヘルペスウイルス感染症
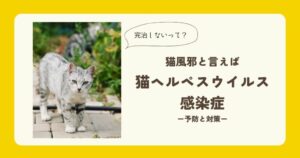
③合併症が怖い:猫カリシウイルス感染症
ワクチンの接種は、健康状態を確認してからの接種が原則です(※風邪気味・下痢などがある場合は延期)。
子猫の場合は生後2ヶ月を過ぎたあたりから接種が可能になり、成猫でも、初回接種→1ヶ月後に追加→年1回のブースター接種という流れが推奨されます。
④必要に応じた治療(風邪・外傷など)
外での生活が長かった子、急な環境の変化に晒された子は、免疫力が落ちていることもあり、風邪をひきやすくなっています。
- 鼻水、くしゃみ、目やに、涙:いわゆる「猫風邪」の初期症状
- 目が開かない、白く濁っている:結膜炎や角膜炎の可能性
- 傷、出血、腫れ:ケンカによる外傷や膿瘍の可能性
- 食欲がない、動かない:内臓疾患や発熱の可能性
こうした症状を見つけたら、できるだけ早く病院を受診しましょう。

日常サポートの基本
次に、安全な空間を保つためのサポートについてです。
- 食事管理(年齢・体調に合わせたフード選び)
→ 子猫、成猫、老猫で必要な栄養は異なります。 - 清潔なトイレ環境
→ 砂の種類によってトイレ嫌いになる子も。相性を観察しましょう。 - 快適なケージや寝床の用意
→ 安心できるスペースは、心の安定にもつながります。 - ストレスを減らす接し方
→ 無理に触らず、見守る時間も「ケア」のひとつ。
こちらも順番に解説していきます。
①食事管理(年齢・体調に合わせたフード選び)
保護されたばかりの猫は、心も体も不安定。
そしてその中身──“どんなフードをどれだけ与えるか”は、年齢や体調によって大きく変わってきます。
- 1.子猫:とにかく「こまめに・しっかり栄養」
-
一度にたくさんは食べられないため、生後2ヶ月頃までは1日5〜6回、生後半年までは1日3〜4回を目安にします。
栄養価の高い子猫用フードを中心に、体をつくる栄養素(タンパク質・脂質・カルシウムなど)をたっぷり含んだものを選びましょう。
- 2.成猫:安定期こそ「太りすぎ・偏り」に注意
-
1歳を過ぎた成猫は、1日2回程度の食事でOK。
ただし、避妊・去勢手術後の猫は代謝が落ちて肥満になりやすいので、フードの量やカロリーは調整が必要です。 - 3.シニア猫:消化に優しく、食欲を引き出す工夫を
-
7歳頃からは「シニア期」に入り、活動量が減り、筋肉量や免疫力が落ちてきます。
11歳頃からは老化の兆候が徐々に出てきて食欲が低下しやすくなります。
固いドライフードを嫌がる子には、ウェットフードやふやかしフードに切り替えるとよく食べてくれることも。15歳からは老齢期に入り、老化現象が顕著になります。
また、腎臓や心臓に不安がある子には、療法食の検討を。
食べる量が減ってきたら、回数を増やして少量ずつ与えるのがポイントです。あわせて読みたい 高齢の保護猫を迎えたい!家族になるための飼い方と注意点 今回のテーマは『高齢の保護猫の飼い方』というテーマについて。 猫ちゃんを家族に迎えたいけれど、どうせなら、一番必要とされている子を助けたい…そう思っているあな…
高齢の保護猫を迎えたい!家族になるための飼い方と注意点 今回のテーマは『高齢の保護猫の飼い方』というテーマについて。 猫ちゃんを家族に迎えたいけれど、どうせなら、一番必要とされている子を助けたい…そう思っているあな…
②清潔なトイレ環境
猫が快適にトイレを使えるために、以下の3つを意識しましょう。
- 清潔さ:1日1〜2回はうんち・おしっこを取り除く。
- 静かな場所:人通りの少ない場所に設置。騒がしい場所は避ける。
- 十分な数:多頭の場合は「猫の数+1個」が理想。
また、猫砂には紙・鉱物・おから・木などさまざまな種類があります。
ただし、猫によって好みが分かれるため、「合わない」とトイレ自体を我慢してしまうことも…。
- トイレの外に排泄してしまう
- 入ったあとすぐ出てしまう
- 砂をかかずに飛び出していく
これらの行動が見られたら、トイレ環境の見直しが必要かもしれません。
砂の種類・トイレの大きさ・置き場所・掃除頻度を一つずつ確認してみてください。
③快適なケージや寝床の用意
ケージは「閉じ込める」場所ではなく、猫にとっての“安心できる個室”として考えましょう。
保護直後の猫にとって、自分だけの落ち着けるスペースはストレスを減らし、人との距離も自然と縮まりやすくなります。
上下運動ができる2〜3段ケージなら、スペースが限られていても快適に過ごせます。
トイレ・水・フード・寝床の配置は、猫の行動を観察しながら調整しましょう。
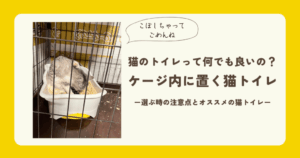
慣れてきたら徐々にフリーにして、行きたいときにケージに戻れる「安心の避難所」として使うのが理想です。
ケージが難しい場合、ダンボール箱・キャリーケース・ブランケットをかけたカゴなど、“こもれるスペース”をいくつか用意してあげましょう。
フカフカすぎるよりも、体がすっぽり入る小さめサイズが落ち着きやすい子もいます。
④ストレスを減らす接し方
保護されたばかりの猫は、過去の経験から人間に不信感を抱いていたり、環境の変化に強いストレスを感じていたりします。
そんな猫たちにとって、「無理に触られない」「しつこく構われない」ということが、何よりも安心につながるのです。
- 目をじっと見つめない(猫にとって威嚇のサインになります)
- 静かにゆっくり動く(急な動作や大きな音は驚かせる原因に)
- 無理に触らず、近くにいるだけでOK(人の存在に慣れてもらう時間)
猫との関係づくりは、“距離感”がとても大切です。
「触る=愛情」ではなく、“そばにいてくれる安心感”が、心をひらく第一歩になります。
- ごはんやおやつを同じ時間・同じ場所であげて、生活にリズムと安心を。
- 名前をやさしく呼びながら、気配で存在を伝える。
- 「触らない」けど「そっと見ている」ことで、猫が自分から近づいてくれるのを待つ。
焦らず、比べず、その子のペースに合わせて関わることが、ストレスを減らす最大のケアです。
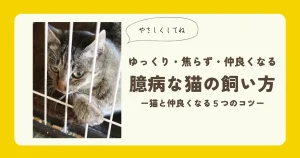
おわりに:「できる範囲で、でも手を抜かない」
医療もお世話も、「完璧にできなくちゃいけない」と思うとしんどくなってしまいます。
まずは 命を守ること、そして 少しずつ信頼関係を築くこと。
それが、保護猫にとっても保護主さんにとっても優しいスタートになります。

脱・ひとりぼっち保護活動
支援を受けながら続ける知恵と工夫
ひとりで保護活動を続けている保護主さんが、人とつながり、支援を受けながら活動していくための具体的なヒント