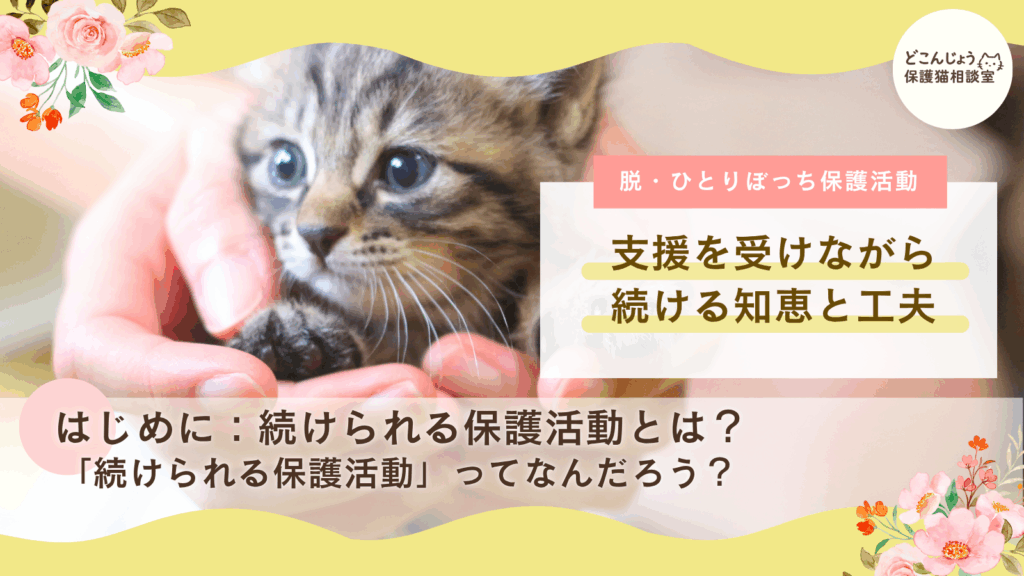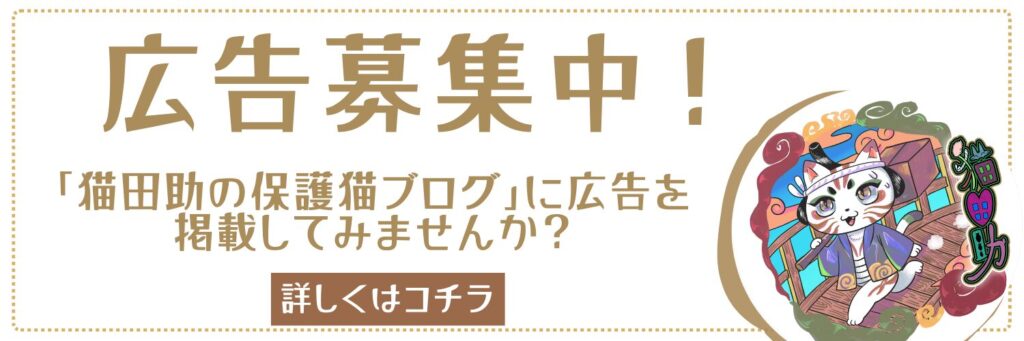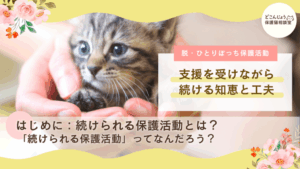「もう少し自分に余裕があれば…」
「支援してくれる人がいれば…」
「なかなか里親が見つからない…」
保護猫活動をしていると、こうした思いに直面する場面が少なからずあります。
命を前にすると、がんばってしまう。
がんばりすぎて、気づいたら「続ける」ことが難しくなっていた…
そんな経験を持つ方は少なくありません。
けれど、本当に大切なのは「今日も猫とちゃんと向き合えてる自分でいること」。
猫を助けたい。その気持ちを続けるために、活動そのものも持続可能な形にしていく必要があります。
そのために必要な視点。それが、次の3つです。
①「つながる」ことを恐れない
ひとりで始めた活動でも、どこかのタイミングで「誰かに頼る」「つながる」ことが必要になります。
それは、同じように保護活動をしている仲間かもしれないし、近所の動物病院、あるいは行政、SNSでつながった見知らぬ人かもしれません。
「全部自分でやらなきゃ」と思ってしまうのは、優しさの裏返し。
でも、つながることで命のリレーはもっと遠くまで届きます。
つながり続けるヒント
その時に大事なのは、お互いの世界に干渉しすぎないことです。

それぞれ、経験や対応してきた猫の数、そこに至るまでの活動や経緯などバックグラウンドが違います。
特に猫の保護活動はその思いの強さに比例して、人間関係のトラブルに繋がることも多いのですが、一番は目の前のことにのめり込みすぎてしまうから。
だからこそ、強制ではなく相手に敬意を持ちつづけられる距離感を保ちましょう。
②「伝える」ことをあきらめない
支援が届かないのは、「伝えていないから」かもしれません。
保護猫たちのこと、日々の悩み、必要としていること—それを言葉にして届けないと、支援する側もどう応援していいかわからないのです。
もちろん、最初からうまく言えなくても大丈夫。
写真1枚でも、短い言葉でも、「見せる」「伝える」ことは立派な支援への第一歩。
「ひとりじゃない」と感じられる瞬間は、画面の向こうにも、必ず存在しています。

伝えるツール
いま、たくさんのSNSがあります。
X(Twitter)やInstagramなど、それを利用しているユーザーによって雰囲気や層が違ってきます。
自分が発信しやすいもの、無理なく続けられるものを選びましょう。
また、フォロワーを増やすために猫に負担がかかることも本末転倒です。
あくまでも猫ファーストで、猫たちの日々を発信していきましょう。
③「ゆだねる」ことを覚えていく
保護猫活動の中で、1番難しいこと。
それは「自分じゃない誰かに託すこと」かもしれません。
譲渡もそう。物資の受け取りもそう。
自分の手を離れる瞬間が必ずあります。
でも、猫を助けることは「自分が全部やる」ことではなく、「助けられる仕組みに乗せる」こと。
信じて、ゆだねて、見守る—それもまた、保護活動の大切な力のひとつです。

譲渡の先に
保護猫は譲渡したら終わりではありません。
命を守り、育て、親の手を離れ自立していく。
猫の保護は子育てと似ていると常々思います。
譲渡というのは、自立・独立の節目です。
里親さんともゆるく長くつながり続けていけるように、コミュニケーションが取れる・伝わる場所を作っておきましょう。
おわりに:「あなたが続けられる形で」
猫の数も、保護主の形も、それぞれ違うのが当たり前。
「できることから、できる範囲で」「助けられる人を増やす視点で」
—そんなふうに、あなたが「無理なく続けられる形」を見つけていくことが、結果的に猫たちの未来を明るくする力になります。
「ひとりで抱えなくていいんだ」と思える仲間が、ここにいることを、どうか忘れないでくださいね。

脱・ひとりぼっち保護活動
支援を受けながら続ける知恵と工夫
ひとりで保護活動を続けている保護主さんが、人とつながり、支援を受けながら活動していくための具体的なヒント