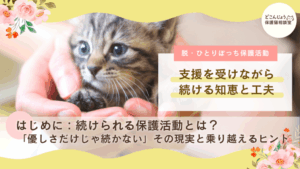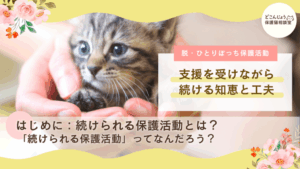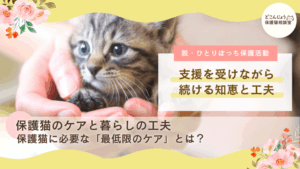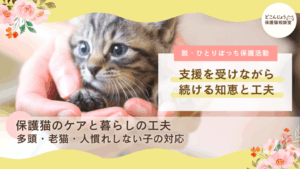「もうひとりで頑張らなくて大丈夫」
保護活動をしていると、疲れたって言えない時がある。
でも続けていくためには、頼ったっていい。
このマニュアルでは、ひとりで保護活動を続けている保護主さんが、人とつながり、支援を受けながら活動していくための具体的なヒントをまとめました。
保護主のためのガイドマニュアル
Module 1|はじめに:続けられる保護活動とは?
- 1.保護主のリアルな悩みと限界
-
保護活動を続ける中で、時間・体力・お金・孤独感で心が折れる人も多いです。助けたい想いが続けられなくなる前に、悩みや限界を見つめ直しましょう。
あわせて読みたい 「優しさだけじゃ続かない」その現実と乗り越えるヒント 保護活動を続けるには「つながる」「伝える」「ゆだねる」の3つが鍵。他者と関わり、思いを言葉にし、無理せず助けを借りることで、活動は持続可能になります。
「優しさだけじゃ続かない」その現実と乗り越えるヒント 保護活動を続けるには「つながる」「伝える」「ゆだねる」の3つが鍵。他者と関わり、思いを言葉にし、無理せず助けを借りることで、活動は持続可能になります。 - 2.持続可能性のための3つの鍵(つながる・伝える・委ねる)
-
保護活動を続けるには「つながる」「伝える」「委ねる」の3つが鍵になります。他者と関わり、思いを言葉にし、無理せず助けを借りることで、活動は持続可能になっていきます。
あわせて読みたい 「続けられる保護活動」ってなんだろう? 「続けられる保護活動」のためには、助けを求められる“つながり”、想いを共有する“伝える力”、そして自分ひとりで抱えこまない“委ねる工夫”が鍵となります。
「続けられる保護活動」ってなんだろう? 「続けられる保護活動」のためには、助けを求められる“つながり”、想いを共有する“伝える力”、そして自分ひとりで抱えこまない“委ねる工夫”が鍵となります。
Module 2|保護猫のケアと暮らしの工夫
- 1.保護猫に必要な「最低限のケア」とは?
-
保護猫に安心を届ける第一歩は、最低限の医療と毎日の暮らしを整えること。ウイルス検査やワクチン接種、清潔なトイレや快適な寝床…。小さなケアの積み重ねが、信頼と健康を育てます。
あわせて読みたい 保護猫に必要な「最低限のケア」とは? 保護猫に安心を届ける第一歩は、最低限の医療と毎日の暮らしを整えること。ウイルス検査やワクチン接種、清潔なトイレや快適な寝床・小さなケアの積み重ねが、信頼と健康を育てます。
保護猫に必要な「最低限のケア」とは? 保護猫に安心を届ける第一歩は、最低限の医療と毎日の暮らしを整えること。ウイルス検査やワクチン接種、清潔なトイレや快適な寝床・小さなケアの積み重ねが、信頼と健康を育てます。 - 2.多頭・老猫・人慣れしない子の対応
-
多頭・老猫・人慣れしない猫には、それぞれ異なるケアが必要です。無理をせず、猫のペースに合わせた環境づくりと接し方が、安心と信頼を育てる第一歩になります。
あわせて読みたい 多頭・老猫・人慣れしない子の対応 多頭・老猫・人慣れしない猫には、それぞれ異なるケアが必要です。無理をせず、猫のペースに合わせた環境づくりと接し方が、安心と信頼を育てる第一歩になります。
多頭・老猫・人慣れしない子の対応 多頭・老猫・人慣れしない猫には、それぞれ異なるケアが必要です。無理をせず、猫のペースに合わせた環境づくりと接し方が、安心と信頼を育てる第一歩になります。
- 保護スペースと生活リズムの工夫
Module 3|SNSで支援を得る基本設計
- インスタ・LINE・Xの使い分け
- 共感を呼ぶ写真とことば
- 応援されるアカウント運用の基本
Module 4|モノとお金の支援を受ける
- 物資支援の届け方(Amazonリスト/支援ネットワーク)
- 寄付をお願いするときのマナーと工夫
- 自立型活動への一歩(講座・情報提供型の収益)
Module 5|地域とつながる、仲間とつながる
- 保護主ぐるぐる支援の活用法
- 信頼関係のつくり方
- 相談・連携できる人を増やす